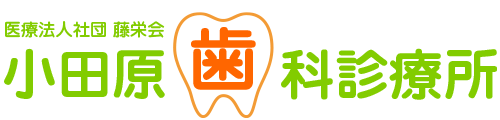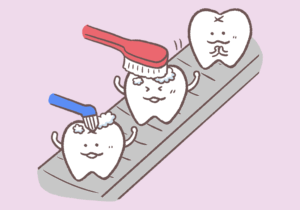口呼吸はお口の健康リスクを高める!原因と対策を知って虫歯と歯周病を予防しよう

こんにちは。
小田原歯科診療所、院長の伊藤です。
「気が付くと口がぽかんと開いている」「朝起きたときに喉がカラカラに乾いている」「ご家族からいびきを指摘された」といった経験はありませんか?これらの症状は、口呼吸が原因かもしれません。
口呼吸の習慣をそのままにしておくと、お口の健康を損なうリスクが高まってしまうため注意が必要です。
今回は、口呼吸によって引き起こされるお口のトラブルと予防法をわかりやすく説明します。
口呼吸がもたらすお口の健康リスクとは?
口呼吸と鼻呼吸は、単なる呼吸方法の違いと考えられがちですが、口呼吸はお口の健康にさまざまな悪影響を与えます。
唾液の分泌が減少し、口臭や虫歯、歯周病のリスクが高まる
口呼吸は直接的にお口の中の乾燥を引き起こします。お口の中が乾燥すると、細菌の増殖を抑える唾液の分泌が減少し、細菌が増えやすくなります。その結果、口臭や虫歯、歯周病のリスクが高まります。
子どもの顎の発達を妨げ、歯並びが悪くなる
子どもの正常な上顎の発達には、舌が上顎に触れることが重要です。舌が上顎を押し上げることで、顎が広がって永久歯が生えるスペースが十分に確保されます。
しかし、口呼吸になると舌の位置が下がり、上顎を押し上げることができないため、上顎の成長が妨げられます。その結果、歯の並ぶスペースが不足し、歯並びが悪くなります。
さらに、歯並びが悪いと歯みがきがしにくくなり、磨き残しが増えて、虫歯や歯周病のリスクも高くなってしまいます。
もしかして口呼吸?確認してみよう!
無意識に口呼吸になっているか、次のチェックリストで確認してみましょう。
- お口が開いていることが多い
- いびきをかいている
- 唇がよく乾燥し、荒れやすい
- 鼻が詰まりやすい
この中で複数当てはまる項目がある場合、口呼吸が習慣になっている可能性があります。
鼻呼吸への切り替えを意識しよう
鼻で呼吸をすると、空気が鼻の中で加湿・加温されるだけでなく、細菌やほこりなどの異物も取り除かれます。これらの働きによって、お口の中が乾燥しにくくなり、細菌の増殖も防ぎやすくなります。
また、鼻呼吸を続けることで舌が正しい位置に保たれ、顎の発達や歯並びにも良い影響があります。
日中は意識して鼻呼吸を心掛け、寝ている間も鼻呼吸を続けるための工夫をしてみましょう。
口呼吸を防ぐためにできること
お口周りの筋肉(口輪筋)を鍛える体操
お口周りの筋肉(口輪筋)が弱いと、自然とお口が開いてしまいます。
「あ・い・う・え・お」と大きくお口を開けて発声することで、鍛えることができます。
飲酒を控える
アルコールを摂取すると体内の水分が奪われ、脱水状態になりやすくなります。その結果、唾液の分泌が減り、お口の中が乾燥しやすくなります。
特に寝る前の飲酒は、気道を広げる筋肉が緩み鼻が詰まりやすくなるため、口呼吸をしやすくなります。そのため、飲酒は適量を守ることが大切です。
寝るときに「口テープ」を活用する
睡眠中にお口が開いてしまうのを防ぐために、専用の「口テープ」を貼る方法があります。テープを軽く貼ることで、お口が開くのを抑え、鼻呼吸を促すことができます。
ただし、無理に貼ると苦しく感じることがあるため、慣れるまでは試しながら調整するようにしましょう。
虫歯や歯周病のセルフケア
正しい歯磨きを習慣付ける
歯と歯ぐきの境目に歯ブラシを当て、小刻みに動かしながら磨くのがポイントです。
デンタルフロスや歯間ブラシを使うと、歯と歯の間の汚れを効果的に落とすことができます。
歯ぐきを強くする食生活を意識する
ビタミンCにはコラーゲンの合成を促し、傷ついた組織の再生を助ける働きがあります。赤パプリカやアセロラなど、ビタミンCを多く含む食品をバランスよく摂ることで、歯ぐきの健康をサポートしましょう。
定期的に歯科検診を受ける
自覚症状がない場合でも、歯医者で定期的な検診を受けて、歯周病の早期治療や予防につなげることが大切です。
歯医者では歯ぐきの状態を詳しく確認し、問題が見つかった場合は、すぐに適切な処置を行います。
まとめ
口呼吸が唾液減少を引き起こし、虫歯や歯周病のリスクが高まると聞くと、不安に感じる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、適切なケアと習慣改善で虫歯や歯周病は予防できます。
当院では、虫歯や歯周病の早期治療・予防のために定期的な歯科検診をおすすめしています。口呼吸の習慣や歯ぐきの腫れ、出血など、気になることがありましたら、お気軽にご相談ください。