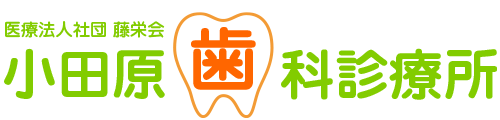食べにくい・飲み込みにくいと感じたら?年代別に見る嚥下機能低下の原因と対策
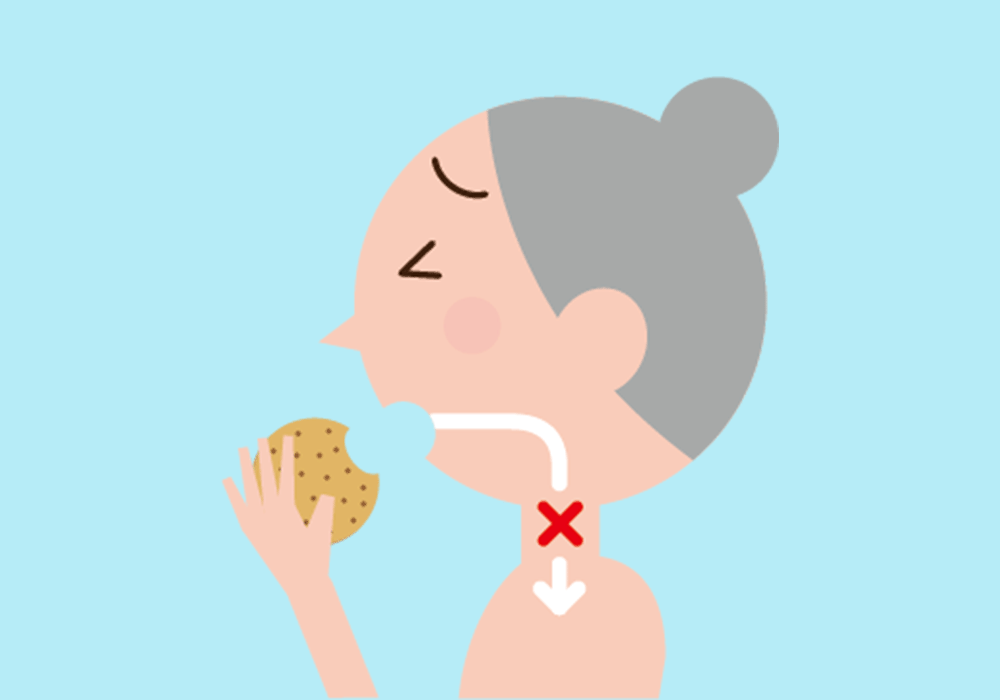
こんにちは。
小田原歯科診療所、院長の伊藤です。
「食事中にむせることが増えた」「以前より飲み込みにくくて、なんだか食事が億劫になってきた」などと感じることはありませんか?それは嚥下(えんげ)機能の低下が原因かもしれません。
今回は、年代によって異なる嚥下機能低下の原因と、それぞれのケア方法についてご紹介します。
嚥下とは
嚥下とは、食べ物を安全に胃まで送り込むための一連の動作のことです。これは、私たちが毎日行なっている自然な動作ですが、実は多くの器官の筋肉や神経が連携する複雑な仕組みで成り立っています。
嚥下機能は年齢とともに衰えるイメージがありますが、若い方でも姿勢が悪かったり、生活習慣が乱れていたりすると、嚥下に関するトラブルが起こることがあります。
嚥下の仕組み
まず、お口の中で食べ物を噛み砕き、唾液と混ぜて飲み込みやすい「食塊(しょっかい)」を作ります。この食塊が喉の奥に運ばれると、「嚥下反射」という飲み込むための自然な反射が起きます。嚥下反射が起こると、気管は蓋がされ、食道への道が開かれ、食べ物が食道へと送り込まれます。嚥下反射は、私たちが食べ物を安全に飲み込むために、重要な役割を果たしているのです。
嚥下障害とは
嚥下障害とは、お口の中の食べ物や飲み物をうまく飲み込めない状態のことです。加齢や特定の病気などが挙げられます。
嚥下障害の症状には、食べ物が喉に詰まる、引っかかる感覚や痛み(嚥下困難)、食事のときのむせ、体重の減少などがあります。
年代別の嚥下機能低下
年代別に、嚥下機能が低下する主な原因を紹介します。
20~30代
20〜30代では、ストレートネックが嚥下機能低下の原因となることがあります。
スマホやパソコンなどを長時間使用し、前かがみの姿勢でいるとストレートネックになりやすく、嚥下に必要な筋肉の動きが制限されます。ストレートネックになると顎が上を向きやすくなり、飲食物が気管に入りやすくなってむせたり、うまく飲み込めなくなったりすることがあります。
40~50代
40~50代になると、加齢によって嚥下機能が少しずつ低下し始めます。筋力の低下や嚥下反射の鈍化、唾液の分泌量の減少、咽頭や食道の粘膜が薄くなることなどが原因で嚥下困難が起こります。
さらに、嚥下反射が鈍くなると、飲食物が誤って気管に入る「誤嚥」が起こることがあります。このとき、飲食物や唾液に含まれる細菌が気管を通って肺に入ることで、誤嚥性肺炎が発生する場合があります。
60代以上の世代
高齢になると、虫歯や歯周病によって歯を失うことが多くなります。また、舌の動きや咀嚼(そしゃく)する力、唾液の分泌、味覚も低下します。
お口の中のさまざまな機能が衰えると、食べ物を咽頭に送る力が弱くなり、嚥下機能にも問題が起こりやすくなります。
さらに、嚥下機能が低下すると、咽頭に唾液や食べ物が残りやすくなり、誤嚥のリスクが高まります。
年代別おすすめの ケア方法
嚥下機能の低下は、日常的なケアで予防できます。
20~30代
20~30代におすすめなのは、まず、スマホを使うときの姿勢を見直すことです。画面を見るときは、なるべく顔を上げて、首が前に突き出ないように意識しましょう。
そして、食事はよく噛んで、ゆっくりと味わいましょう。虫歯や歯周病予防のために、食後の歯みがきも忘れずに行なってください。
40代以上
40代以上の方には、お口や喉の筋肉を鍛えるトレーニングと定期的な歯科検診をおすすめします。
さらに、将来の健康を守るために、嚥下機能だけでなく、全身の健康状態も定期的にチェックしましょう。病気の早期発見や予防につながります。
まとめ
当院では、日常生活で実践できる簡単なお口の筋力トレーニングや姿勢に関するアドバイスをご提供しています。また、通院が難しい方には、訪問歯科診療も行なっており、ご自宅でのお口のケアをサポートいたします。まずは、お気軽にご相談ください。